お気軽にお問い合わせください
医療マーケティング完全ガイド|クリニックの集患・分析・戦略を徹底解説
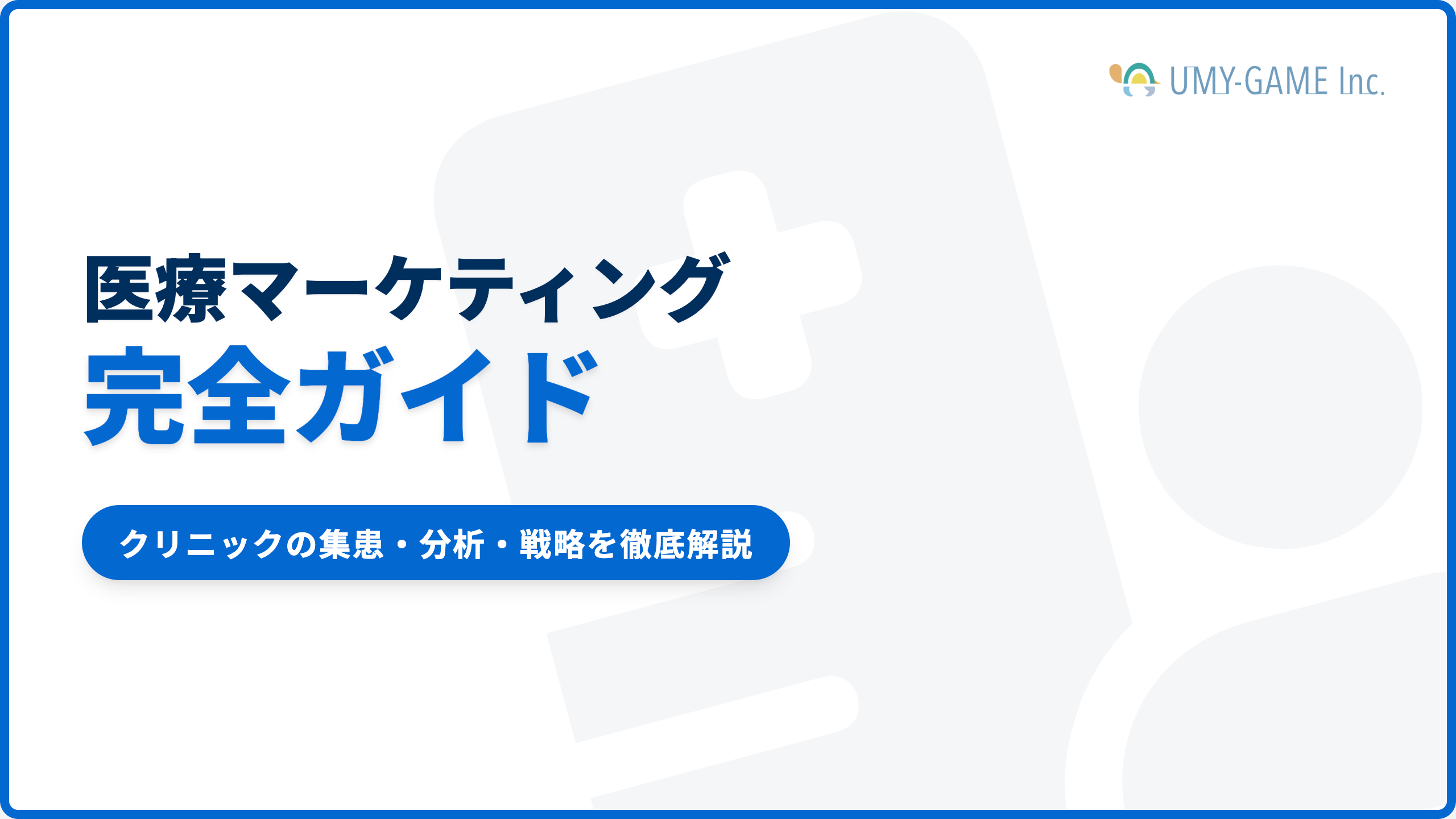
医療の世界でも、患者さんに自分のクリニックを知ってもらい、来てもらうための工夫がとても大切になっています。これを「医療マーケティング」といいます。医療マーケティングを上手に行うことで、クリニックの良さを多くの人に伝えられ、患者さんを増やすことができます。
この記事では、クリニックが患者さんを集めるための方法や、集めた情報をもとにどのように改善していくか、そして具体的な戦略の立て方についてわかりやすく解説します。医療マーケティングを理解し実践することで、患者さんに選ばれるクリニックを作りやすくなり、地域の健康を支える役割をよりよく果たせるようになるでしょう。
これから医療マーケティングの基本やポイントを学んでいきましょう。
Contents
医療マーケティングとは?

医療マーケティングとは、医療機関や医療関連サービスが患者や地域社会に向けて、自らの特徴や提供価値を効果的に伝えるための戦略的な活動を指します。一般的なマーケティングと比べて、医療マーケティングは患者の健康と安全を最優先に考慮し、法令遵守や倫理的配慮が一層求められます。
例えば、医療広告ガイドラインにより、治療効果の過大な表現や誤解を招く表現は禁止されており、情報の正確性と透明性が強く求められています。
一般的なマーケティングとの違い
医療マーケティングは、消費者の単なる購買行動を促す一般的なマーケティングとは異なり、患者の命や健康に直結するため慎重なアプローチが必要です。
一般的な製品やサービスのマーケティングでは、主に消費者のニーズや好みを喚起し、購買を促進しますが、医療分野では患者の症状や健康状態に応じた情報提供や、信頼の構築が不可欠です。
また、医療機関は患者の個人情報を取り扱うため、プライバシー保護や個人情報保護法の遵守も重要となります。
さらに、医療マーケティングは地域の医療ニーズや医療資源の状況を踏まえた戦略設計が求められます。
例えば、過疎地域では訪問医療や遠隔診療のニーズが高まる一方で、都市部では高度医療や専門診療の情報発信が重視されます。こうした地域特性を踏まえたマーケティングは、患者の利便性向上や地域医療の質の向上にも寄与します。
なぜ今、医療マーケティングが必要なのか
昨今の医療環境は、高齢化の進展や医療技術の発展、医療費の増加により大きく変化しています。
日本の65歳以上の高齢者人口は2024年時点で約29.3%に達し(出典:統計からみた我が国の高齢者(総務省統計局))、これに伴い慢性疾患の管理や在宅医療の需要が増加しています。
このような中、医療機関は多様な患者ニーズに対応しつつ、適切な医療サービスを提供するための情報発信が不可欠です。
また、インターネットやSNSの普及により、患者自身が医療情報を能動的に収集する時代となりました。信頼できる情報を適切に届けることで、患者の選択肢を広げ、医療機関への信頼感を高めることが可能となります。
加えて、医療機関間の競争激化により、特色ある診療やサービスを効果的に伝えるマーケティングの重要性が増しています。
現代の医療マーケティングでは、オンライン診療の普及やデジタル技術の活用も欠かせません。例えば、予約システムや電子カルテ連携、患者向けの健康管理アプリなどを用いることで、患者体験の向上と医療機関の業務効率化が期待できます。
医療機関におけるマーケティングの目的

医療マーケティングとは、医療機関が患者のニーズを的確に把握し、適切な情報提供やサービス改善を通じて、患者の受診行動を促す活動を指します。
多様化する医療環境の中で、単に患者数を増やすだけでなく、医療サービスの質を高めつつ、患者との信頼関係を築くことが求められています。
以下では、医療機関におけるマーケティングの主要な目的を、新規患者の集患、既存患者の継続と信頼構築、医療サービスの質の向上との両立という観点から解説します。
新規患者の集患
医療機関にとって新規患者の獲得は、経営の安定化に直結する重要な課題です。
特に地域医療では、患者の選択肢が増える中で自院の存在感を高めることが求められます。集患の課題は、患者が自分に合った医療機関を選びにくい点や、情報過多による混乱が挙げられます。原因としては、医療情報の非対称性や専門用語の理解困難さが影響しています。
解決策としては、分かりやすい医療情報の発信や、オンライン予約システムの導入、SNSや地域イベントでの情報発信が効果的です。
既存患者の継続と信頼構築
医療機関の持続的な成長には、既存患者との関係維持が不可欠です。患者の継続的な受診は、健康管理の質向上や病状の早期発見にも繋がります。課題は、患者が他の医療機関に流出するリスクや、治療継続のモチベーション低下です。
原因として、医療機関の対応の不一致や情報提供不足が挙げられます。解決策は、定期的なフォローアップや個別の健康相談、患者満足度調査の実施によるサービス改善です。
医療サービスの質の向上との両立
医療マーケティングは単なる集患手段にとどまらず、医療サービスの質向上と両立させる必要があります。患者満足度を高めるためには、診療の質や接遇、施設環境の充実が欠かせません。
課題は、マーケティング施策がサービスの本質を損なう恐れがある点です。原因は、集患重視が過剰になると医療の安全性や倫理性が軽視されがちなことにあります。
解決策としては、医療サービスの標準化や職員教育の充実、患者からのフィードバックを反映した継続的な改善が挙げられます。質の高い医療提供と効果的な情報発信の両立が信頼獲得に繋がります。
医療マーケティングの基本ステップ

医療マーケティングとは、医療機関や関連サービスが患者や利用者に適切に情報を届け、選ばれるための戦略的な活動を指します。医療業界特有の規制や高い信頼性が求められるため、計画的かつ慎重なアプローチが必要です。
ここでは、医療マーケティングの基本ステップを順を追って解説します。
ステップ1:市場分析(地域・競合)
まずは市場の全体像を把握することが重要です。地域の人口構成や健康ニーズ、既存の医療サービスの状況を調査します。厚生労働省の「地域保健・医療計画」など公的資料を活用し、地域ごとの疾病構造や医療資源の偏りを確認しましょう。
また、競合となる医療機関の診療科目やサービス内容、患者層を分析し、自院の強みや弱みを客観視します。これにより、地域の医療ニーズと市場環境を踏まえた戦略が立てやすくなります。
ステップ2:ターゲット設定とペルソナ作成
市場分析の結果をもとに、具体的にどの患者層をターゲットにするかを決定します。ターゲットは年齢、性別、疾患の種類や重症度、生活習慣など多角的に設定することが望ましいです。
さらに、想定される典型的な患者像を「ペルソナ」として具体化すると効果的です。ペルソナを設定することで、マーケティングメッセージやサービス内容を患者のニーズに即した形で設計できます。
たとえば高齢者の慢性疾患患者を対象にした場合、通院の利便性や継続的なケアの提供が重要視されるでしょう。
ステップ3:差別化とポジショニング
医療機関が多い市場で目立つためには、他院との差別化を明確にする必要があります。
診療技術、医師の専門性、施設の設備、患者対応の質など、競合にはない強みを洗い出します。これが「ポジショニング」と呼ばれ、自院のブランド価値を高める要素となります。たとえば、女性専門外来や予防医療に特化することも一つの差別化戦略です。
ポジショニングは患者の選択基準に直結するため、地域のニーズに合致した独自の立ち位置を築くことが重要です。
ステップ4:マーケティング施策の実行
差別化戦略を踏まえ、具体的な施策を展開します。ホームページの充実やSNSの活用、地域向け健康セミナーの開催など、多様なチャネルを通じて情報発信を行います。
医療広告ガイドラインに準拠し、誇大表現を避けながら正確な情報提供を徹底することが肝要です。
また、患者の声を反映したサービス改善やスタッフ教育も継続的に行い、信頼関係の構築に努めます。オンライン診療の導入など、新しい技術も積極的に検討しましょう。
ステップ5:効果測定と改善サイクル
施策の効果を正確に把握し、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回すことが成功の鍵です。
来院患者数や相談件数、ウェブサイトのアクセス解析、患者満足度調査など、定量・定性双方のデータを収集します。これらのデータをもとに、どの施策が効果的であったかを分析し、次の施策に反映させます。
医療機関の信頼性を損なわない範囲で改善を繰り返し、患者に寄り添ったサービスを追求することが求められます。
分析に使える手法とツール
アンケートや満足度調査
医療マーケティングとは患者や利用者のニーズを把握し、適切なサービス提供につなげる取り組みです。
最初のステップとして、アンケートや満足度調査が有効です。これらは患者の声を直接収集できるため、具体的な改善点や強みを明確にできます。たとえば、治療内容の理解度や待ち時間への満足度を質問することで、現場の課題が浮き彫りになります。
実施時は質問の設計に注意が必要で、わかりやすく選択肢を用意することが回答率向上に寄与します。
- アンケートは患者の声を直接反映できる
- 質問設計で回答率と信頼性を高める
- 公的ガイドラインに基づく実施が望ましい
SWOT分析・ペルソナ分析
医療機関が抱える課題の原因を深掘りする際、SWOT分析は有力な手法です。
強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を整理し、内外環境を俯瞰的に把握します。たとえば、地域の競合状況や患者層の変化を踏まえた戦略立案に役立ちます。
さらに、ペルソナ分析を活用すると、典型的な患者像を具体化し、ターゲットに刺さる情報発信が可能です。患者の年齢、職業、ライフスタイルを詳細に設定し、マーケティング施策の精度向上を図ることができます。
- SWOT分析で内外環境を整理し課題の本質を把握
- ペルソナ分析でターゲット像を具体化
- 公的資料を活用し手法の理解を深める
Webサイトのアクセス解析(Google Analytics)
現代の医療マーケティングにおいて、Webサイトのアクセス解析は不可欠です。Google Analyticsは無料で導入でき、多様なデータを収集・分析できます。
訪問者数、ページ滞在時間、流入経路を把握することで、患者がどの情報に興味を持っているかがわかります。例えば、予約ページの離脱率が高ければ、操作性の改善が必要です。
医療機関のWebサイトに適したKPI設定やプライバシー保護にも注意を払い、患者情報の安全管理を徹底することが求められます。
- Google Analyticsで訪問者行動を可視化
- 離脱率や流入経路から改善点を特定
- 個人情報保護を遵守しつつ分析を実施
電子カルテ・レセコン分析ツールの活用
医療マーケティングとは、医療データの活用で効率的なサービス提供を目指すことも含まれます。電子カルテやレセプトコンピュータ(レセコン)から得られる診療情報は、患者層の傾向分析や診療の質向上に役立ちます。
これらのデータを分析する専用ツールを導入すれば、疾患別の患者数推移や再来院率、処方傾向を把握可能です。
ただし、個人情報保護法に基づき匿名化や取り扱いルールの厳守が必須です。
実践できるマーケティング施策一覧

SEO/MEO対策
医療マーケティングとは、患者に適切な医療情報を届けるための戦略的手法を指します。その中でもSEO(検索エンジン最適化)とMEO(マップエンジン最適化)は、オンラインでの認知度向上に不可欠です。
SEOは検索結果で自院のホームページを上位に表示させる施策で、患者が症状や治療法を検索した際に見つけやすくなります。MEOはGoogleマップなどの地図サービスでの表示を最適化し、地域密着型の集患に有効です。
医療機関において、受診する医療機関を探すためにインターネットを活用している患者は約4割ですが、受診予定の医療機関に関する情報(診療時間などの基本情報や専門性などの詳細な情報)を確認する目的での利用が多いです。
また、特に「近くの病院」を探す患者や緊急性の高いユーザーにとって、MEO対策は新規患者獲得に非常に効果的であり、検索結果の上位表示や口コミがその要因となります。※
※出典: 患者を増やし定着させるにはネットでの正確な情報提供と医師のコミュニケーション力が重要・ネット予約はニーズ拡大の予想―患者500人超の調査結果を公表(株式会社eヘルスケア)
SNS活用(Instagram・LINE公式など)
SNSは若年層から中高年層まで幅広く活用されており、医療現場の情報発信に適しています。Instagramでは視覚的にわかりやすい健康情報や院内の雰囲気を伝えることができ、LINE公式アカウントは予約や問い合わせ対応、リマインド配信に便利です。
ただし、個人情報保護や広告ガイドラインを順守し、誤解を招く表現は避けることが重要です。
オンライン広告(Google広告・SNS広告)
オンライン広告はターゲットを絞り込んで効率的に情報を届けられる点が強みです。Google広告は検索キーワードに連動し、潜在患者のニーズに直接アプローチできます。
SNS広告は年齢や地域、興味関心に基づくセグメント配信が可能で、費用対効果の最適化が図れます。広告費の投資対効果を高めるためには、定期的な効果測定と内容のブラッシュアップが欠かせません。
日本広告審査機構の指針に従い、誇大広告や不確実な表現は避ける必要があります。
院内でのチラシ・掲示物
院内でのチラシや掲示物は、来院患者に直接情報を届ける有効な手段です。待合室や診察室前に健康情報や予防接種、キャンペーン案内を掲示することで、患者の関心を引きやすくなります。
厚生労働省の指針に沿い、誤解を招かない表現を用いることが求められます。適切なデザインと配置で読みやすさを確保し、患者の理解促進につなげることが重要です。
効果的な掲示物は、患者満足度の向上にも寄与します。
ホームページ・ブログ運用
ホームページやブログは、医療機関の信頼性を高める情報発信の基盤です。専門用語を噛み砕きながら、診療内容や医師紹介、最新の医療ニュースを定期的に更新することで、訪問者の理解と関心を深められます。
SEO対策も施した運用が求められ、検索エンジンからの流入増加に寄与します。
医療マーケティングの法的・倫理的配慮

医療広告ガイドラインに準拠した情報発信
医療マーケティングとは、医療機関や製薬企業が患者や消費者に向けて医療サービスや製品の情報を提供し、適切な選択を促す活動を指します。
しかし、医療情報の特性上、誤解を招く表現や過剰な期待を抱かせる表現は社会的・法的に問題視されやすく、法令遵守が不可欠です。厚生労働省が定める「医療広告ガイドライン」では、患者の安全と正しい医療理解を守るため、広告表現に細かな制限を設けています。
例えば、治療効果の保証や副作用の軽視、科学的根拠のない情報提供は禁止されており、客観的なデータに基づいた説明が求められます。
また、医療機関の実績や診療内容を紹介する際は、誤認を招く可能性のある「最良」「唯一」といった断定的表現を避ける必要があります。これらのルールに沿った情報発信は、消費者の信頼を得ると同時に、法的リスクの軽減にもつながります。
誇大表現・ビフォーアフターNGなどの注意点
医療マーケティングの表現で特に注意すべきは、誇大広告やビフォーアフターの画像使用です。景品表示法や医療広告ガイドラインでは、実際の効果を過度に強調し消費者の誤認を招く表現を厳しく規制しています。
例えば、治療結果を比較するビフォーアフター写真は、個人差が大きい医療分野において誤解を生むことが多いため、原則として使用が禁止されています。
また、「絶対に治る」「副作用なし」といった断定表現は、科学的根拠が十分に示せない限り避ける必要があります。
代わりに「効果には個人差があります」「副作用のリスクが存在します」などの注意喚起を添えることが望ましいです。患者に正しい判断材料を提供するためには、エビデンスに基づいた情報の透明性と誠実な説明が求められます。
これらの注意点を遵守することで、医療マーケティングとは単なる販促活動ではなく、患者の健康と安全を最優先に考えた信頼性の高い情報発信であることを示せます。具体的には、以下のチェックリストを活用し、広告内容を点検すると効果的です。
医療マーケティングとは、単に製品やサービスを売るための手段ではなく、患者の健康を守りながら正確な情報を届ける責任あるコミュニケーションです。適切な法的・倫理的配慮を徹底し、信頼性の高い情報発信を心がけましょう。
医療DXと連携した最新トレンド

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)は、医療現場の効率化や患者体験の向上を目指し、医療マーケティングの領域でも注目されています。医療マーケティングとは、医療機関が患者のニーズに応え、適切な情報提供やサービス改善を行うための戦略的な取り組みを指します。
最新の医療DX技術を活用することで、患者一人ひとりに合わせた精度の高いマーケティングが可能となり、医療機関の競争力向上につながっています。
電子カルテ・CRMと連携したマーケティング
電子カルテは患者の診療情報を一元管理するシステムであり、CRM(顧客関係管理)と連携させることで、患者の過去の診療履歴や健康状態を踏まえたコミュニケーションが可能になります。
これにより、患者の健康リスクを把握し、予防医療や定期検診の案内を適切なタイミングで送ることができるのです。
例えば、糖尿病患者に対して生活習慣改善の情報を提供したり、高齢者には骨折予防の運動プログラムを案内したりと、個別化されたアプローチが実現します。
予約・問診システムから得るデータ活用
オンライン予約や問診システムの導入は、患者の利便性を高めるだけでなく、集積したデータの活用によるマーケティング効果も期待されます。予約の履歴や問診内容から患者の健康傾向やニーズを分析し、的確な情報発信やサービス改善に役立てられます。
例えば、特定の症状が多い時期に関連する健康セミナーを開催したり、受診後のフォローアップメールで継続的なケアを促すことが可能です。
デジタルチャネル(LINE/公式アプリなど)
LINEや公式アプリなどのデジタルチャネルは、患者との日常的なコミュニケーションを支える重要なツールです。これらのチャネルを活用することで、診療予約のリマインド、健康情報の配信、キャンペーン案内などがスムーズに行えます。
特にLINEは日本国内で月間利用者数が9,400万人を超え、幅広い年齢層にリーチ可能なため、医療機関の顧客接点として効果的です。
また、公式アプリでは患者の診療履歴や検査結果の閲覧機能を備え、医療機関と患者の信頼関係構築に寄与しています。これらのデジタルチャネルは、医療マーケティングの多様化と個別化を促進する鍵といえるでしょう。
医療DXと連携した最新トレンドは、電子カルテやCRMの連携による個別化マーケティング、予約・問診システムからのデータ活用、そしてLINEや公式アプリといったデジタルチャネルの活用が軸となっています。
これらの技術を適切に組み合わせることで、患者の満足度向上と医療機関の経営改善が期待できるため、今後ますます医療マーケティングとは何かを理解し、医療DXを取り入れることが重要です。
成功事例

ここでは弊社ウミガメ株式会社のマーケティング施策による成功事例をご紹介いたします。
【ホームページ未整備から集患加速】K歯科(関西)
課題:
ホームページがない状態で開業し、Web経由の新患はゼロ。競合医院との差別化を図るためにおしゃれで情報性の高いWeb構築を検討していた。
導入後の成果:
- ホームページ制作後、MEO連携で月40人以上の新患を獲得
- インプラントなどの自費患者も増加
【分院開業の推進力に】Oy歯科(東京都)
課題:
月50人の新患はいたが、さらなる集患や自費増を目指していた。InstagramとSEOを組み合わせた複数施策を一元的に実施する体制を構築したかった。
導入後の成果:
- 新患数:月50人 → 月70人超に増加
- 売上:月800万円 → 月1,330万円
- 年商:1.6億円、自費売上:5,000万円
【審美・矯正患者の集患成功】A歯科(秋葉原)
課題:
セラミック治療の問い合わせが月3件と少なく、専門性の高い治療が埋もれていた。SNSやコンテンツでの訴求を強化したかった。
導入後の成果:
- セラミック治療の問い合わせが最大で1日3件に増加
- 美容目的の患者層も獲得
まとめ

医療マーケティングとは、患者や利用者のニーズを的確に捉え、適切な情報発信やサービス提供を通じて信頼関係を築く取り組みです。
現代の医療環境では、デジタル技術の進展や患者の情報リテラシー向上により、効果的なマーケティング戦略が求められています。
まずは自院の強みや地域特性を分析し、患者視点での情報発信を心がけることが重要です。厚生労働省のガイドラインを遵守しつつ、正確かつ分かりやすい情報提供を行うことで、信頼性を高められます。
今すぐ始める一歩として、小さな改善から取り組み、継続的に効果を検証しながら進めてみませんか?
